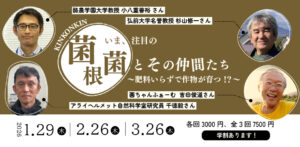報告)2024年の「哲学講座」でお話しいただいたこと
内山節さんの『哲学講座』 テーマ:報復される時代
2024年11月16日(土)13:00開講 ~ 17日(日)15:00閉講
講師:内山節(うちやま・たかし)氏
内山節さんによる「哲学講座」(第13回)を、2024年11月に埼玉県戸田市の農文協本社で開催しました。オンラインもあわせて30名の方に参加いただきました。講義テーマは「報復される時代」でした。
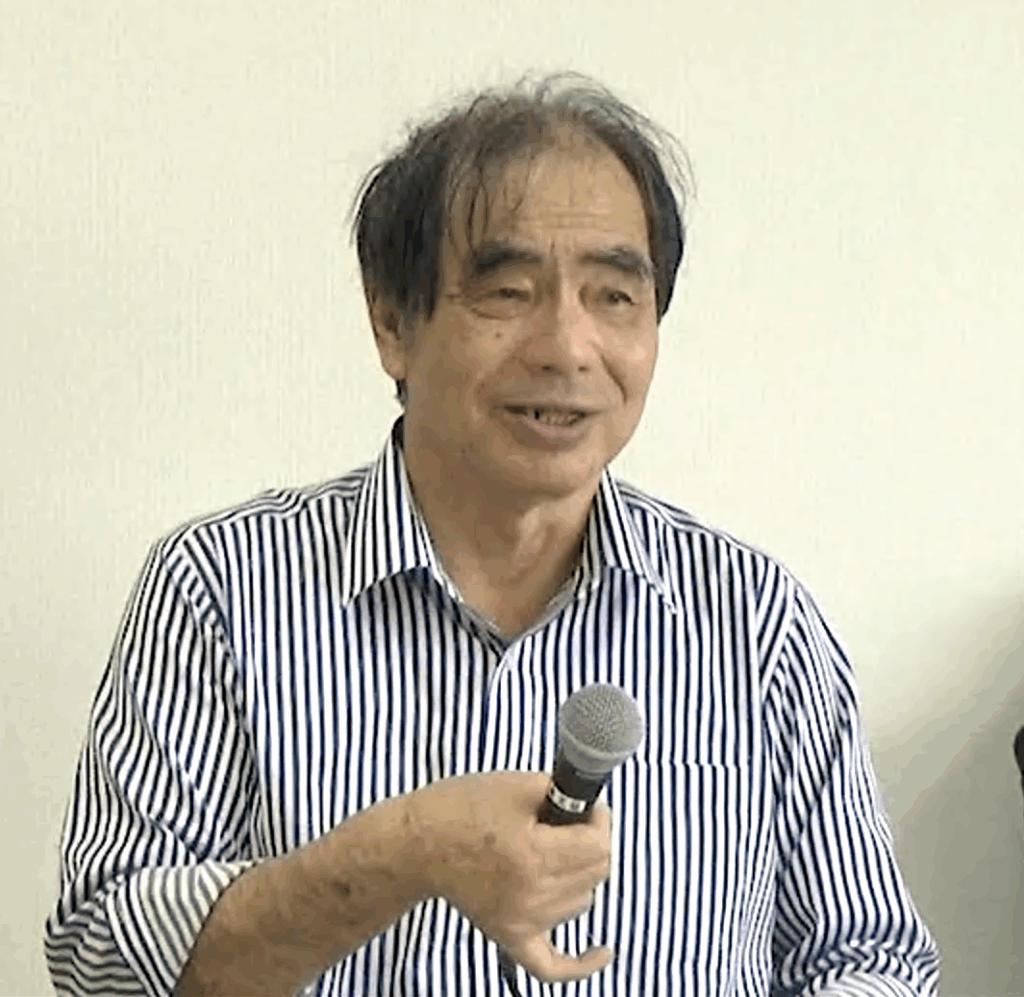
今の世界をひとことでいえば「報復される時代」だと内山さんはいいます。「この世界は自然と自然、自然と人間、人間と人間の関係でできている。その3つが相互に関係を結び、全体の関係がある。近代的社会はそれらの関係を歪ませてきた。関係の歪みが『報復』という形で現れている」と。
たとえば、異常な暑さや頻発する水害を内山さんは「自然からの報復」と捉えます。「人は昔から、『ここまでなら自然が許してくれるだろう』という諒解をもとに、その時代に調和した自然を作ってきた」。そのような自然と共存する技術のひとつに「川をもって川を制する」山梨の「信玄堤」があります。一方、農文協本社にもほど近い荒川や利根川は、近代的治水技術で人間の都合のいいように流れを変えられてできた姿だといいます。「川は太古の記憶をよみがえらせるように動いていく」という河川工学者の高橋裕さんの言葉があるそうです。人工的に強い力で抑え込んだだけの川に囲まれた首都圏で、いつ洪水が起きてもおかしくない。
「報復」は、人間と人間の関係の歪みからも起きています。たとえば、ロシアへの制裁に同調しない国が多いのは「旧植民地国の人々からの報復」、トランプ現象は「近代的理念への報復」と捉えられるといいます。
近代の世界がもっていたさまざまな矛盾があらわになるなか、近代の枠組みとは異なる発想が必要ではないかと内山さんは説きます。ここで示唆的なものとして紹介されたのが、ドキュメンタリー映画『阿賀に生きる』。新潟水俣病の被害をうけた地域を舞台にしながらも、公害や企業・行政の対応の告発や賠償闘争ではなく、それにもかかわらず阿賀野川とともに生きていく人たちの世界を主軸に描いた映画です。「明るい未来を戦いとる」というより、「ここで生きる」という宣言になっています。象徴的なこととして、住民たちは地域にお地蔵さんと祈りの場をつくります。「ここで生きる」ために、それがまさに必要だったからです。

また、公害問題は自然と人間の関係の歪みが引き起こすものですが、どうすれば解決したといえるのでしょうか? 企業や行政が謝罪や賠償をすれば解決なのか? そうではない、と内山さんは言い、「海が許してくれたら解決」という水俣のある漁師の言葉を紹介しました。
最後に内山さんは、「共同体の世界、それとともに生きてきた人が語る思想の世界。こうしたものをもっと見直すことが、この瓦解する社会で生きるうえで重要になっていくでしょう」と結びました。
質問・討議や交流会も大いに話が弾みました。会場には『洪水と水害をとらえなおす』著者で上掲『阿賀に生きる』の制作委員会代表も務めた大熊孝先生や『水辺の小さな自然再生』著者の中川大介さんも参加されており、川との人との関係についてより深く話しあうことができました。
2025年も11月末に内山さんの哲学講座を開催します。詳しくはボタンをクリック